【令和7年4月24日(知財高裁 令和6年(行ケ)10095号)】
【キーワード】
商標法4条1項15号、混同
【事案の概要】
原告は、専門性を持った防災士と呼称する指導的役割を持つ人材の養成、確保、活用等により、わが国の防災と危機管理に寄与すること等を目的とする特定非営利法人である。原告は、以下の登録商標(以下「引用商標」という。)の商標権者であり、また、その事業において、「防災士」という商標(以下「引用使用商標」といい、引用商標とあわせて「本件各使用商標」という。)を使用している。
登録番号:商標登録第4833713号
商標:
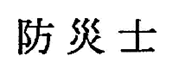
指定商品・役務:
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授(防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の検定試験、防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の教授、防災専門知識及び技能・防災又は災害情報公表の知識及び技能・救急救命知識及び技能・避難誘導知識及び技能の質の証明を含む。)、動物の調教、図書及び記録の供覧、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・制作又は配給、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、放送番組の制作、映写フィルムの貸与、テレビジョン受信機の貸与、ラジオ受信機の貸与、図書の貸与、レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与、録画済みビデオディスクの貸与
被告は、「食育」「健康」「環境」「防災」の普及に関し持続可能な事業等を行い、福祉の向上と国民の豊かな生活の実現に寄与すること等を目的とする一般社団法人である。被告は、以下の登録商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。なお、同商標は令和3年12月2日(以下「本件登録査定日」という。)に登録査定が行われている(登録査定時の商標権者は株式会社クレバーエンタープライズであり、令和6年3月12日に被告に移転した)。
登録番号:商標登録第6521920号
商標:日本食育防災士(標準文字)
指定商品・役務:
第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授、教育上の試験の実施、教育の分野における情報の提供、実地教育、個人に対する知識の教授、知識又は技芸の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。)、図書及び記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作、コンピュータを利用して行う書籍の制作、書籍の制作(広告物を除く。)、インターネットを利用して行う映像の提供、放送番組の制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
原告は、本件商標について、原告の使用する引用使用商標と類似するものであり、混同を生じさせる商標であるため、商標法4条1項15号に該当する等の無効理由(他の無効理由は同法4条1項6号、7号、10号、11号又は19号。)が存在するとして、商標登録無効審判を請求した(無効2023-890093)。これに対して、特許庁は、請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)を行ったため、原告は、その取消しを求めて、本件訴訟を提起した。
【争点】
・商標法4条1項15号該当性
【判決一部抜粋】(下線は筆者による。)
第1~第4(省略)
第5 当裁判所の判断
1・2 (省略)
3 取消事由3(商標法4条1項15号該当性の認定判断の誤り)について
⑴ 「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」について
商標法4条1項15号は、周知表示へのただ乗り及び希釈化を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標使用者の業務上の信用の維持及び需要者の利益の保護を目的とするものであるから、同号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等がこの他人との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同を生ずるおそれ)がある商標を含むものと解するのが相当である。
そして、同号の「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(最高裁第三小法廷平成12年7月11日判決・平成10年(行ヒ)第85号・民集54巻6号1848頁〔レールデュタン事件〕参照)。
⑵ 本件商標と本件各使用商標との類似性の程度
ア 前記したところによれば、本件商標は、商標法4条1項10号又は同項11号の適用との関係では、本件各使用商標と類似するものではないが、本件商標の外観のうち「防災士」の部分、称呼のうち「ボウサイシ」の部分は、それぞれ本件各使用商標と同一であり、観念においても「防災に関する何らかの資格、その資格を有する者」という要素において共通性が認められる。
イ 本件商標は、本件各使用商標との関係で、このような共通性を有する限度では類似性を有する一方、本件商標の指定役務の需要者であって、防災又は防災に関する資格について関心を有する者(前記1⑶エ)の間においては、本件各使用商標は周知である。そうすると、本件商標「日本食育防災士」は、本件各使用商標「防災士」と区別して識別することができるものではあっても、その需要者からみれば、「防災士」と全く無関係なものではなく、何らかの関連性を有する資格ではないかという連想を生じさせ得るものである。
⑶ 本件各使用商標の周知著名性及び独創性の程度
ア 前記1⑶エのとおり、本件商標の指定役務の需要者には、防災又は防災に関する資格について関心を有する者が含まれており、このような需要者の間においては本件各使用商標は周知であると認められる。
イ 本件各使用商標は、「防災」の語に資格者を示す「士」を加えたにすぎず、その独創性の程度は高いとはいえない。
⑷ 本件商標の指定役務と原告の業務に係る役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度、役務の取引者及び需要者の共通性、その他取引の実情
ア 原告は、防災に関する民間資格である「防災士」の資格の認証、防災士の資質向上を図る事業や防災に関する啓蒙活動等を行うことを目的とし(前提事実⑴ア)、前記1⑶イによれば、原告は自ら実際にそれらの活動を行っているほか、原告の認定を受けた多数の地方自治体や大学等が、防災士養成研修実施機関として、防災士の資格試験受験のための研修を実施するなど、原告の「防災士」に係る役務の提供は、原告のみならず、原告が認めた関係団体を通じても行われていること、原告から認証を受けた防災士や防災士の団体である日本防災士会が、地域、職場等の防災訓練における指導、災害対応マニュアルの作成支援、防災に関する講演等の啓発活動等、防災に関するさまざまな活動を行っていることが認められる。
しかるところ、防災と食に関連するテーマは、本件登録査定日前から、防災士が講師として参加する防災に関する地方自治体等の行う啓蒙活動等において繰り返し取り上げられている(甲152~161)。このことは、「防災」と「食」とが密接に関連しており、防災に関係する食の問題が原告の業務に係る役務(防災士の育成及び活用、防災等を目的とする団体・個人との連携、講演会・シンポジウム等の啓蒙活動等)の対象分野の一つであることを示すものである。
他方、本件商標の指定役務(技芸・スポーツ又は知識の教授、教育上の試験の実施、セミナーの企画・運営または開催、電子出版物の提供、放送番組の製作等)は、被告の事業の一つである「防災・非常用途の食糧品及びツールに関する商品情報の収集、危機管理情報の収集、分析、提供サービス」(甲41・定款第2条)に係る役務として提供されるときは、いずれも、防災と食をテーマとするという意味において、本件各使用商標を使用して行う原告の啓蒙活動等の業務と対象分野が重なることになる。被告代表者は、現に災害時の食料の確保、備蓄、配給、食の安全等について普及活動等を行っており(甲46~62、105)、その活動を紹介する記事の多くでは「日本食育防災士」に対する言及がされていることが認められる(甲51~53、55~58、60)。
そうすると、本件商標の指定役務と原告の業務に係る役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度は、高いというべきである。
イ 本件商標の指定役務の需要者と本件各使用商標に係る原告の業務の需要者は、いずれも防災又は防災に関する資格に関心を有する者が含まれるから、需要者の共通性が認められる。
ウ その他の取引の実情
静岡県は、原告から防災士養成研修実施機関の認定を受けているほか、平成17年以降、名称に関する原告の承諾を得て、独自に「静岡県ふじのくに防災士」(平成21年までは「静岡県防災士」)を養成しており、原告が認証する「防災士」とは別のものであることの注意喚起とともに、ホームページにおいて告知している(甲12、92、133、137の6-4、弁論の全趣旨)。このことは、逆にいえば、一般に「防災士」の名称は、その前に付加される語句如何にかかわらず、原告の認証する「防災士」と関係するものであるとの誤解が生じやすいという現状認識を示すものということができる。
⑸ 混同のおそれについての判断
以上の事情は、本件登録査定日のほか、その約2か月前である本件商標の登録出願日においても(商標法4条3項)認められる。これらの事情を総合すると、本件商標をその指定役務に使用するときは、その需要者の普通に払われる注意力を基準としても、その役務が原告の「防災士」と何らかの関係を有する防災関係の資格であって、原告又は原告が認めた関係機関が運営・管理するものの業務に係る役務であるとの混同(広義の混同)を生ずるおそれがあるということができる。
⑹ (省略)
⑺ 取消事由3についての結論
したがって、本件商標は商標法4条1項15号に該当するから、これを否定した本件審決の判断には誤りがあり、取消事由3には理由がある。
4 結論
よって、その余の点を判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきものであるから、主文のとおり判決する。
【検討】
商標法4条1項15号は、同法4条1項10号から14号に定める商標以外であっても、出所の混同を生ずるおそれのある商標が存在するところ、当該商標について登録を認めないという総括的な規定である。そのため、商標が非類似であっても、具体的な取引の実情等より混同を生ずるおそれがある場合、同号により登録が認められないことがある。また、同号の「混同」とは、広義の混同をいうとされており、商標の類似性の程度、周知著名性、独創性、商品・業務の関連性等が判断要素とされる(最判平成12年7月11日〔レールデュタン事件〕)。
本件では、「日本食育防災士」との登録商標について、「防災士」との文字からなる本件各使用商標とは非類似と判断され、商標法4条1項10号及び11号との無効理由は否定されたものの、取引の実情等を考慮して、同項15号の「混同を生ずるおそれ」があると判断され、同号の該当性が肯定された。
本件において、商標法4条1項15号該当性における判断要素として、従前の裁判例と同様、商標の類似性の程度、周知著名性、独創性、商品・業務の関連性等があげられているが、本件各使用商標の周知著名性については、特定の需要者にとって「周知」であると認定されており、商品・役務の全体の需要者における周知著名性は認定されていない。
同号該当性はあくまで諸事情を柔軟に考慮することが必要であるため、商標の周知著名性は、必ずしも商品・役務の全体の需要者を対象とする必要はないものといえる。
以上
弁護士 市橋景子


