【平成27年12月24日(知財高裁平成27年(行ケ)第10084号)】
【判旨】
商標法4条1項10号の無効理由が存在するとした審決に関し、引用商標の周知性が認められないとして、同審決を取り消した。
【キーワード】
商標法4条1項10号、商標法47条
【事案の概要】
原告は、平成17年1月25日、本件商標につき商標登録出願をし、同年8月30日、登録査定がされ、同年9月16日、設定登録がされた。被告は、平成26年6月26日、本件商標の登録無効審判請求をした。特許庁は、平成27年3月31日、以下の主旨で、同商標登録を無効とする旨の審決をし、その謄本は、同年4月9日、原告に送達された。本件は、この審決の取消訴訟である。
なお、本件登録は、いわゆる除斥期間経過したものである(すでに「商標権の設定の登録の日から五年を経過(商47条)」した登録である)ため、商標法4条1項10号で無効とするためには「不正競争の目的」の存在が必要である。
(審決)
本件商標の登録は、商標法4条1項10号に該当する。
(1) 周知性
引用商標(引用商標1~引用商標3)は、いずれも、平成12年7月ころまでに周知性を獲得し、その後、現在に至るまで、被告により使用されている。したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、被告が取り扱う米国コネチカット州所在の米国法人エマックス社(エマックス社)の製造販売に係る電子瞬間湯沸器(本件電子瞬間湯沸器)を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた。
(2) 商標の類否
本件商標と引用商標とは、類似する。
(3) 指定商品の類否
本件指定商品と引用商標に係る使用商品とは、同一又は類似する。
(4) 不正競争の目的の有無
原告は、本件商標の登録出願時において被告が取り扱う商品を表示するものとして周知であった引用商標と類似する本件商標を、引用商標が商標登録されていないことを奇貨として、登録出願をし、登録を得た。したがって、本件商標は、不正競争の目的でその登録を受けた場合に該当する。
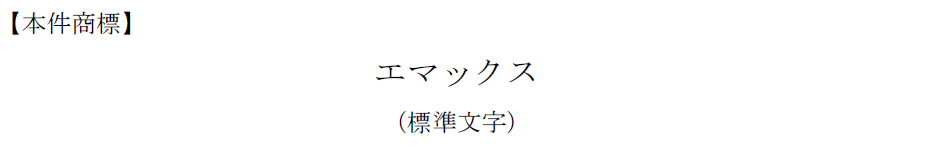 (指定商品又は指定役務) 第11類 家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類 |
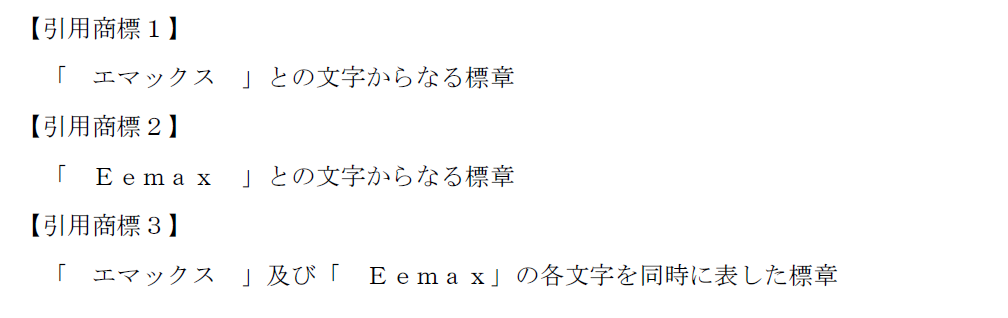 |
【争点】
争点は、引用商標の周知性の有無である。
【判旨抜粋】(下線部は筆者による)
第4 当裁判所の判断
1 当事者等の認定 ・・・省略・・・
2 取消事由1(引用商標の周知性の有無)について
(1) 周知性に関係する事情について
下記掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件商標の周知性に関係する事情として、次の事実が認められる。
ア 宣伝広告
② 平成11年3月26日、被告は、日経産業新聞紙上に本件電子瞬間湯沸器の宣伝広告を掲載した。同広告中には、「エマックス」(引用商標1)との表示がある。(甲7)
イ 新聞・雑誌記事及びテレビ放送
② 平成6年10月20日、日本流通産業新聞に、被告が、エマックス社との間で本件電子瞬間湯沸器の独占販売代理店契約を締結したとの内容の記事が掲載された。同記事中の本件電子瞬間湯沸器の写真には、「EemaX」との表示が確認できる。(甲4)
③ 平成6年10月31日、日刊水産経済新聞に、被告が、エマックス社との間で本件電子瞬間湯沸器の独占販売代理店契約を締結したとの内容の記事が掲載された。同記事本文中には、「エマックス」(引用商標1)との記載があるほか、同記事中の本件電子瞬間湯沸器の写真には、「EemaX」との表示が確認できる。(甲5)
④ 平成7年9月30日、旬刊(月3回)の日本工業技術新聞に、被告が出展した本件電子湯沸器が話題を呼び好評を博した旨の記事が掲載された。同記事の見出しや本文には、「エマックス」(引用商標1)の記載がある。(甲10)
⑤ 平成9年6月ころ、経済誌である「経済界」6月10日号に、被告及び被告代表者の紹介と共に、被告が本件電子瞬間湯沸器のアジア地域における独占販売権を取得した旨の記事が掲載された。同記事中には、「エマックス」(引用商標1)との記載がある。(乙1)
⑥ 平成14年4月9日、本件電子瞬間湯沸器が、KRY山口放送「さわやかモーニング」で紹介された。同放送の映像中には、「エマックス EemaX」(引用商標3)との表示が確認できる。(乙4の2の2)
⑦ 平成15年11月ころ、専門誌である「建築設備と配管工事」11月号に本件電子瞬間湯沸器を紹介する記事が掲載された。同記事中には、「エマックス」(引用商標1)との記載がある。(乙2)
⑧ 平成16年10月22日、大分合同新聞に、被告が中国企業との間で本件電子瞬間湯沸器の販売代理店契約を締結したことを紹介する記事が掲載された。同記事中には、「エマックス」(引用商標1)との記載がある。(乙4の2の4、弁論の全趣旨)
ウ 実演展示
エ 販売台数等
② 被告作成の平成12年7月付けの納入先一覧(甲12)によれば、本件電子瞬間湯沸器の納入先は、国内の157社であったことが認められる。ただし、その販売期間及び販売台数は不明である。(甲12、13の1~3)
③ 平成15年10月30日付けの大分合同新聞の記事(乙4の2の3)によれば、本件電子瞬間湯沸器の発売以来の累計の納入台数は、約5000台とされる。(乙4の2の3)
④ 平成6年7月から平成18年6月までの被告の会社全体における広告宣伝費は、おおむね100万円前後~250万円程度であり(ただし、平成14年7月~平成15年6月期は、約330万円である。)、同展示会費は、おおむね120万円前後よりは下回る額である(ただし、平成7年7月~平成8年6月期は約510万円である。もっとも、約7万円という年もある。)。(甲36の1~12、乙5)
(2) 周知性の有無について
ア 前提
ところで、前記第3の1及び第4の1によれば、本訴当事者間においては、本件電子瞬間湯沸器の需要者又は取引者として想定すべき者は、電気を熱源とする瞬間湯沸器の需要者又は取引者に限られるものではなく、ガスを熱源とするものも含む家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器全体の需要者又は取引者であることで争いがないところ、電気を熱源とする瞬間湯沸器とガスを熱源とする瞬間湯沸器とは、同じ用途に使用され、熱源の相違によって利用者が異なるとする事情は認められない・・・。また、本件電子瞬間湯沸器が特定の地方で集中的に又は専属的に販売されるものであるとする事情はないから、引用商標が、全国のいずれかの地域において、上記に説示した地理的範囲において周知であるか否かを考慮する・・・。
イ 検討
そうすると、本件証拠上、被告自身による引用商標に関する宣伝広告等は活発とはいえない上、新聞・雑誌等によりこれが報道された機会も少ないと認められる一方、引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器の販売台数等は明らかではなく、全国的規模の市場に対する販売実績は極めて少ないものと推測される。このような宣伝広告及び販売実績等を考慮すると、家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器又は電気を熱源とする同瞬間湯沸器の市場規模を子細に確定するまでもなく、いずれの引用商標も、本件商標の登録査定時において周知性を有していたとは認め難い。なお、被告が自社ホームページで宣伝活動をしたことは、ホームページを開設することが誰でも直ちに行える以上、それのみで周知性を裏付けるものとはならない。・・・
ウ 小括
【解説】
1. 周知性の判断枠組み
このような日常使用の一般的商品の場合の周知性の判断枠組みについては、昭和58年6月16日(東京高裁昭和57年(行ケ)第110号「DCC事件」等で判示されているほか、特許庁の商標審査基準(4条1項10号の1.(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf))でも採用されている。
逆に、取引形態が特殊な商品又は役務(例えば、医療用医薬品のように特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務)に係る商標(商標審査基準(4条1項10号の5.)については、周知の対象者(需要者)はその筋の専門家間での周知でも足りる。本件「電子瞬間湯沸器」に関しては、そのような特殊な事情はないという判断になったものと思われる。
2. 周知性の判断材料
引用商標の周知性の立証責任は、無効主張する側(無効審判請求人)にある。
本件では、裁判所は「需要者又は取引者の範囲を家庭用の壁掛型の瞬間湯沸器の需要者又は取引者とした場合、一見して僅少である」などとして、引用商標の周知性を認めなかったが、被告(無効審判請求人)は、上記第4の2(1)にあるように、引用商標の周知性立証のための資料を相応に示しているようにも見え、少し厳しい判断のようにも感じるところではある。
ただ本件では、被告によって、被告の販売台数が明らかにされなかった(上記第4の2(2)イ)。そうなると、裁判所としても、「上記第4の2(1)」の事情(かつ客観的裏付けのあるもの)を断片的に捉えざるを得ず、当該証拠に示された内容から、販売台数や広告宣伝の回数等をダイレクトに認定する他になかったのだと思われる。仮に、販売台数が明らかにされ、それが相応の台数であれば、その販売台数に見合っただけの宣伝広告を行っていたという推認が働くだろうから「一見して僅少である」という判断にはならなかった可能性もあったのではないかと考えられる。
一方で、本件の販売台数は、被告側の事情なので、通常被告が容易に示すことができる事情である(仮に、個別の販売台数を示すのが難しいとしても、各年度のP/L等から、大凡の販売台数は示すことができたのではないかと思われる)。本件で被告が販売台数を示すことができなかった理由は不明であるが、明らかにしなかったことによる不利益が、上記立証責任の負担に合わせて被告の負担になってしまったとしても、致し方ないところのように思われる。
(文責)弁護士 高野芳徳


