【令和6年3月11日(知財高裁 令和5年(行ケ)第10095号)】
【キーワード】
商標法3条1項2号、商標法3条2項、色彩のみからなる商標、ブランド
【事案の概要】
原告は、次の色彩のみからなる商標(商願2018-133223。以下「本願商標」という。)について、第3類、第14類、第16類、第18類及び第35類の商品又は役務を指定商品又は役務として、商標登録出願(原出願)を行ったところ、特許庁より、拒絶査定を受けたため、同年8月30日、拒絶査定不服審判(不服2021-13743号)を請求した。しかし、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)がなされたため、原告は、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
<本願商標>
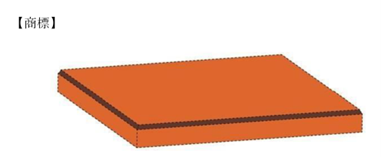
<商標の詳細な説明>
|
商標登録を受けようとする商標は、色彩の組合せのみからなるものであり、箱全体において、橙色(RGBの組合せ:R221、G103、B44)、上部周囲に茶色(RGBの組合せ:R94、G55、B45)とする構成からなる。なお、商標見本における破線は、箱の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。 |
【争点】
・商標法3条2項該当性
【判決一部抜粋】(下線は筆者による。)
第1~第3(省略)
第4 当裁判所の判断
1 原告は、本願商標は原告がその商品の包装箱の色彩として長期、独占的かつ継続的に使用した 結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものになって おり、独占適応性が否定されるものでもない旨主張する。この主張は、本願商標が、指定商品との関係で商標法3条1項3号に該当するとしても同条2項に該当し、指定役務との関係では同条1項6号該当性が否定されるとの趣旨をいうものと解されるので、以下、その前提で検討する(原告は、指定商品との関係で本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした本件審決の判断部分は、本件審決の取消事由としていない。)。
2 色彩のみからなる商標と商標法3条2項等について
(1) ・・(略)・・色彩は商品等に自ずと付随する特性という一面を不可避的に有するところ、通常はこうした商品特性にすぎない色彩が自他商品役務識別力を有するといえるためには、使用による識別力の獲得その他の特段の事情が必要になると解される。この点について平成26年改正は何ら触れておらず、商標法3条1項3号、6号、同条2項等の解釈・適用に(すなわち、色彩以外の商品特性と同じ土俵での議論に)ゆだねている。・・(略)・・
(2) このような観点から、本願商標の特徴を具体的に検討するに、本願商標は、別紙商標目録記載のとおり、橙色(RGBの組合せ:R221、G103、B44)と茶色(RGBの組合せ:R94、G55、B45)の色彩の組合せからなり、箱全体において橙色、上部周囲に茶色とする構成からなるものである。
願書の商標の詳細な説明の記載に照らすと、本願商標は、全体が橙色の「箱」状の物品を想定して、その「上部周囲」(上面と側面が接合するラインを指すものと理解される。)に沿って、輪郭を縁取るように茶色が付されている構成からなるものと理解され、その意味で、立体的形状と色彩の結合商標類似の要素も含まれているといえる。もちろん、同説明中に「商標見本における破線は、箱の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない」と明記されていることから、本来的な意味での立体的形状と色彩の結合商標ではなく、分類としては「色彩の組合せのみからなる商標」であることに変わりはないと解されるが、本願商標が「『立体的形状と色彩の結合商標』類似の要素も含まれている『色彩の組合せのみからなる』商標」という特徴を有することを正しく理解し、その特徴に即応した判断が求められるというべきである。
(3) 被告は、本願商標の橙色と茶色の色彩、組合せ及び色彩の付される位置はいずれもありふれたものであり、これに近似する表示全般を本願商標と見分けることは困難である、本願商標に近似する色彩は、様々な商品の包装箱において多数の事業者によって使用されている実情がある(包装箱等の色彩に関する被告提示事例)、などと主張する。
確かに、橙色と茶色は同系色で、ファッションの分野でも橙色と相性がよく合わせやすい色とされている(乙16)と認められるほか、色彩のわずかな違い程度であれば、近似色との識別が困難な場合があること等は、被告の主張するとおりといえる。
しかし、本願商標は、より商標登録のハードルが高いと考えられる単一色の色彩商標と異なることはもとより、単なる橙色と茶色の組合せをもって特定されるものでもなく、上記(2)で述べたとおり、箱全体の橙色とその上部輪郭を縁取るように付された茶色を組み合わせた特有の構成を有するものである。このような構成は、RGB比率の絶妙なバランスと相まって、明るい橙色と落ち着いた茶色のコントラストを通じて橙色の華やかさを強調し、茶色の縁取りが箱の輪郭のシャープさを印象付けるものであり、特に、茶色をあえて上部周囲だけに使用するにとどめたことで、シンプルな中に気品を感じさせる構成になっているといえる。これを単純な「ありふれた色彩の組合せ」というのは、適切な理解とはいえない。・・(略)・・
3 (省略)
4 本願商標の使用による自他商品役務識別力の獲得について
(1) 前記3の認定事実によれば、原告が展開する「エルメス」ブランドは、我が国においても相当の長期間にわたる直営店等での商品の販売や公式ウェブサイトその他のウェブサイト、全国紙、駅構内や百貨店での屋外掲示、原告の店舗内外のディスプレイ等における広告宣伝により、著名なものとなっていると認められる。その著名の程度は、我が国における歴史の長さ、圧倒的な販売実績、一般消費者への露出の多い活発な広告宣伝等を通じて、あるゆるファッションブランドの中でもトップクラスの地位にあると解される。・・(略)・・
以上の認定に弁論の全趣旨を総合すれば、本件包装箱、ひいては本願商標は、原告のブランド戦略に明確に位置づけられた「エルメス」の象徴として用いられているものと認められる。そして、このような本件包装箱の使用及び宣伝広告を通じて、少なくとも、「エルメス」のような高級ファッションブランド商品の購入者やこれに関心を有する消費者の間では、本願商標を付した本件包装箱(オレンジボックス)は、原告の展開する「エルメス」ブランドに係るものであるとの認識が広く浸透しているものと認められる。
(2) しかし、本願の指定商品及び指定役務は別紙商標目録のとおり多岐にわたり、その中には第3類の革用クリーム、第14類の時計、キーホルダー、第16類の紙製箱等、文房具類、日記帳、写真立て、第18類のリュックサック、カード入れ、傘のように、安価な日用品として取引されることが少なくないものが含まれているから、その需要者は広く消費者一般であると解するのが相当であり、「エルメス」のような高級ファッションブランド商品の購入者やこれに関心を有する消費者に限られないというべきである。・・(略)・・
(3)~(5) (省略)
(6) 小括
・・(略)・・したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告主張の取消事由は認められないことに帰する。本件審決が、指定商品との関係で商標法3条1項3号該当性を認めた上同条2項の適用を否定した判断、指定役務との関係で同条1項6号該当性を認めた判断に誤りはない。
5 その他の論点について
(1) (省略)
(2) 独占適応性の問題について
被告は、本願商標の登録を認めた場合、多数の事業者によって広く使用されている色彩について、本願商標に類似すると判断され得る使用態様が事実上制限されることになり、ファッション分野を中心に、色彩使用の自由が著しく制限され、他の事業者に著しい委縮効果を及ぼすことになる旨主張する。
しかし、まず、本願商標は、単なる橙色と茶色の組合せをもって特定されるものではなく、箱全体の橙色とその上部輪郭を縁取るように付された茶色を組み合わせた特有の構成を有するものであって、その商標登録を認めたからといって、単純に色彩の独占がもたらされるわけではないし、このような特有の構成を備えた色彩の組合せが多数の事業者によって広く使用されているという取引の実情が認められるわけでもない(上記(1)参照)。また、仮に本願商標の登録が認められたとしても、これに類似すると判断される使用態様は、実際上、不正競争防止法2条1項1号の不正競争にも当たる場合が少なくないと解され(被告提示事例イ(ウ)の販売中止の経緯参照)、その委縮効果を過大に評価すべきでない。
(以下、省略)
【検討】
1 「色彩のみ」からなる商標
商標法では、平成26年改正により「色彩のみ」からなる商標であっても商標登録が可能となった(商標法2条1項)。これは、色彩単独でも自他商品識別機能を持つことがあると考えられ、諸外国でも商標登録を認める例が多くなったことによる。
しかし、「色彩のみ」からなる商標は、原則として、商標法3条1項2号、3号又は6号に該当すると判断される(特許庁「商標審査基準」「54.06」参照)。一般に、商取引においては、商品の外装等の商品又は役務に関して付される色彩は、商品又は役務のイメージ、美感等を高めるために多種多様なものの中から選択されて付されるものにすぎず、そのようにして付された色彩が直ちに商品又は役務の出所を表示する機能を有するというものではないからである。
そのため、「色彩のみ」からなる商標が商標登録されるためには、当該商標が使用をされた結果、特定人の業務に係る商品又は役務であることを表示するものとして指定商品又は役務の需要者の間に広く認識されるに至り、その使用により自他商品識別力又は自他役務識別力を獲得していることが必要であり、さらに、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益上の見地からみても許容される事情があることを要する(知財高判令和5年1月24日(令和4年(行ケ)10062号)等)。
2 本件について
本件は、ブランド「エルメス」において商品の包装箱に用いられている配色が「色彩」のみからなる商標(本願商標)として商標登録出願がなされた事案である。
被告(特許庁)は、本願商標の色彩、組合せ及び配置は「ありふれた色彩の組合せ」にすぎないとして商標法3条1項2号に該当する旨が判断された。しかし、裁判所は、本願商標は、色彩のみからなる商標として出願されているものの、「特有の構成」からなるもので、「立体的形状と色彩の結合商標類似の要素も含まれている」として、当該構成から感じる印象(「茶色の縁取りが箱の輪郭のシャープさを印象付ける」「シンプルな中に気品を感じさせる構成」)を踏まえて、当該主張を否定した。
また、被告(特許庁)は、本願商標の登録を認めた場合、他の事業者の色彩使用の自由が著しく制限されるとの独占適応性に関する主張も行ったが、これについても、裁判所は、本願商標の「特有の構成」に着目して、「商標登録を認めたからといって、単純に色彩の独占がもたらされるわけではない」として、当該主張を否定した。
これらの判断を読むと、本願商標について商標登録を認められる流れのようにも思われる。
しかし、裁判所は、結果として、審決の判断を肯定した。
ブランド「エルメス」については、販売期間、広告宣伝等から、一般消費者を基準としても「著名」なものと認められるが、本願商標が付された包装箱については、その認識が広く浸透している需要者は、少なくとも、「エルメス」のような高級ファッションブランド商品の購入者やこれに関心を有する消費者であって、本願商標の指定役務の需要者である一般消費者については、自他商品役務識別力を獲得したとはいえないことが理由である。
3 検討
商標法3条2項の該当性は、あくまで「使用された結果」、特定人の業務に係る商品又は役務であることを表示するものとして、「指定商品又は役務の需要者」の間に広く認識されるに至っていることが必要である。一部の需要者に広く知られているのみでは足らない。同項該当性を主張立証する際には、常に、この点を意識することが重要となる。
なお、本件では商標法3条1項3号に該当することに争いはなく、この点について裁判所は判断していない。しかし、本願商標を「特有の構成」と認定し、「独占的適応性」を認めても問題ないとする判示からすると、裁判所が同号該当性を否定する可能性もあったのかもしれない。
以上
(弁護士 市橋景子)


